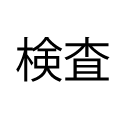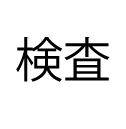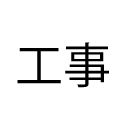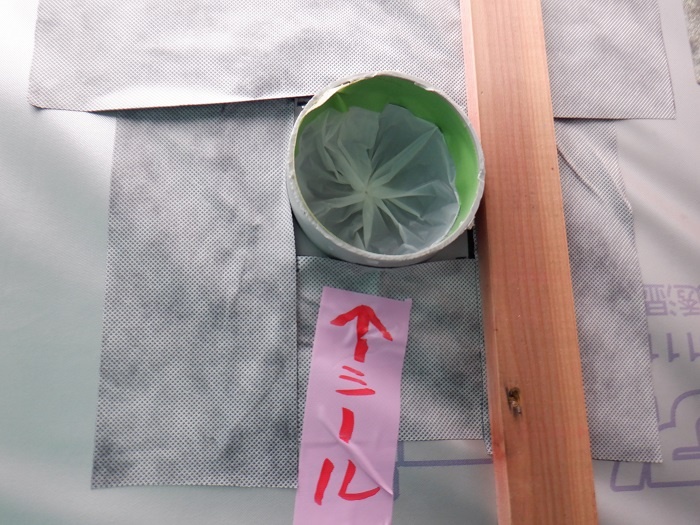危険なブロック塀

写真は、住宅街を歩いていて目に留まったブロック塀です。
ブロックの段数を数えると・・・・・・14段+基礎。
その高さ、なんと3.2ⅿです。
お隣との境界になぜこんな高い塀が必要だったのでしょうか?
隣家の1階部分が全く見えないほどの高さです。
ブロック塀について建築基準法を確認しますと、
1.塀の高さは、2.2ⅿ以下とする。
2.壁の厚さは、15㎝(高さ2ⅿ以下の塀にあっては10㎝)以上とする。
3.控壁は長さ3.4m以下ごとに、壁面から高さの1/5以上突き出したものを設ける。
(高さ1.2ⅿ以下の塀は除く)
このいずれも満たしていない、いわゆる違法なブロック塀です。
おまけにブロックにひび割れもあり、傾きもありました。
大変危険です。
1)~3)については、外見上だけで判断できるものですが、
内部に規定の太さの鉄筋が必要な本数キッチリと入っているのかまでは分かりません。
大きな地震が起こってからでは遅いのです。
阪神淡路大震災から30年。
ブロック塀の倒壊により被害を受けた方も沢山おられます。
ブロック塀は重量もあり危険なので、地震大国の日本では、
できれば他の材料で塀を造ることをお勧めします。
行政によっては、道路側に立てられたブロック塀の解体撤去費は、
補助金が出ることがあるようです。
残念ながらこの写真のような隣地との間のブロック塀には適用されないようです。
このような違法のブロック塀に万が一、
何かあった場合には所有者責任となってしまいます。
気になる方は、一度確認されては如何でしょうか。
関西:鉢嶺 民雄