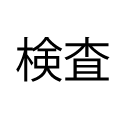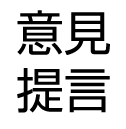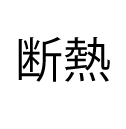筋違(すじかい)

家の構造材のひとつで『筋違』というものがあります。
「すじちがい」ではなく、「すじかい」と読みます。
最近では、間違った字『筋交』が使われていることよく目にします。
ハウスメーカーの図面や木材加工専門であるプレカット業者さえ
『筋交』と図面に書いている。
文字・漢字はそれぞれが意味を持っています。
交わるのではなく、違える(たがえる)のです。
それが『筋違』なのです。
パソコンで手軽に漢字変換すると『筋交』の文字が出てくるので
何の疑いもなく使ってしまっているのが現状ではないでしょうか。
「建築大辞典」(彰国社)には、きちっと『筋違』と書かれており、
筋違とは、四辺形に組まれた軸組に対角線状に入れた補強材。
風や地震力などによる水平力に抵抗し、四辺形が菱形に変形するのを防ぐ。
と記されている。
また、建築基準法施行令第45条は、
残念ながら漢字ではなく、ひらがなで『筋かい』と書かれている。
これには何故?と思ってしまう。
建築基準法は、いわゆる専門家が使う法令集なので『筋違』と漢字で
表現してほしいものです。
その施行令45条には、筋違について下記のように記されています。(抜粋)
・圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3㎝以上で幅9㎝以上の木材を使用したものと
しなければならない。
・筋かいは、その端部を柱とはりその他横架材との仕口に接近して、
ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
・筋かいには、欠き込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするために
やむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。
もう少し日本の木造建築を大切に正確に伝えていってもらいたいものです。
関西:鉢嶺 民雄

斜めの材が「筋違」