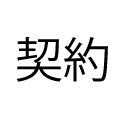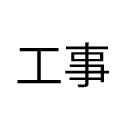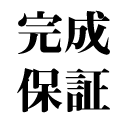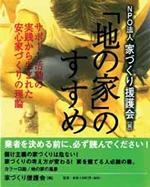悪質リフォーム業者
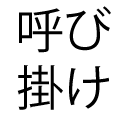
悪質リフォームを繰り返したとみられる容疑者が
建設業法違反容疑で逮捕されたニュースが最近報じられました。
「屋根の瓦がずれている」などと不安をあおり、
不必要な工事の契約を結んでいたとみられているとのことでしたが、
当会にも「突然の訪問業者に[お宅の屋根瓦が外れている]と言われたが、
信用して工事を依頼してよいものか?」と出張相談の依頼がきたことがあります。
業者に「近くの自分の現場からお宅の屋根瓦が外れているのが見えた。
無料で屋根に登ってよく調査してあげる」と言われ、了承してしまいました。
業者は屋根から降りてくるなり、
「これが外れた瓦。早く直さないと雨漏りする。他も危ないので全体の補修が必要。」とし、
後日110万円の見積書を出してきたとのことです。その段階で当会にご連絡されました。
当会で屋根を調査したところ、業者が「外れていた」と差し出した瓦は、
乾燥した土埃のついた瓦で、到底外れて数日雨風にさらされたものではなく、
つい最近外れた感じのものでした。
また外れた箇所の周りの瓦固定針金も、最近切断された切り口の状態でした。
業者が言う「近くの現場」は無く、何軒先の遠目では瓦は判断できません。
当会としては、「故意に瓦を無理やり外された」と判断しました。
また見積書に記載の会社をネット検索してみると疑問点が多く感じられたため相談者に報告し、
その結果、相談者はその訪問業者と連絡を取るのやめました。
訪問業者から上記のように言われたら、その場では話を聞くだけにして、
その後に念のため会社や代表者をネット検索で調べたりしましょう。
それから検討しても遅くありません。

関東:石川 克茂